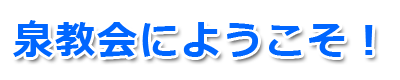「信仰とは何か」
ヘブライ人への手紙11章1~16節
本日は召天者記念礼拝です。先に天に召された方々を思い起こし、共に過ごした日々を感謝し、信仰をもって召された先輩方と地上でも天上でも神様を礼拝する喜びを分かち合うときです。本日の聖書箇所は「信仰とは何か」を明確に語っています。「信仰とは、望んでいる事柄の実質であって、見えないものを確証するもの」であり、昔の人々はその信仰のゆえに称賛されたと記されています。アベルやアブラハムら旧約の信仰者たちは、「信仰を抱いて死にました。約束のものは手にしませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げた」と聖書は語っています。信仰の歴史は、神の言葉を信じて歩んだ人々の名が刻まれた歴史であり、召天者記念礼拝もその延長線上にあります。「召天」は「天に召される」ことであり、「昇天」と異なり、神様によって天に招かれることを意味しています。召天者とは自らの力で天に昇るのではなく、神によって天に召された者たちのことです。「この人たちは皆、信仰を抱いて死にました」との言葉は、「信仰を抱いて生きた」ではなく「死んだ」とあることに意味があります。信仰とは現世での利益や平穏を得るためのものではなく、死の向こうにある神様の約束を信じることに他なりません。自分の「生」だけを見つめていては、死に直面したときに希望を失ってしまうことになるでしょう。『ハイデルベルク信仰問答』は「生きるにも死ぬにも、あなたのただ一つの慰めは何ですか」と問うています。そして「わたしがわたし自身のものではなく、体も魂も、生きるにも死ぬにも、主イエス・キリストのものである」と答えています。主イエスが十字架の死によって、私たちを罪と絶望から買い取ってくださったがゆえに、私たちは生きるにも死ぬにも主のものであることを示しています。「信仰を抱いて死んだ」とは、死の彼方にある約束の成就を信じ、見えない天の故郷を望み見て生きたことを意味しているのです。
泉教会の仲間の一人が、人生の終わりにあって病院スタッフへの伝道に喜びを見出したように、また高齢で受洗した仲間の一人は、病室で賛美歌を歌いつつ神の約束を喜び見たように、信仰とは死をも恐れず、約束の成就を信じて生きる力です。私たちはこの世で全てを得ることはなく、多くをやり残して旅立つのですが、神様は真実なお方であり、神様の御手とともにある業を必ず完成してくださいます。信仰者はその確信によって、まだ手にしていない約束をはるかに望み見て喜んでいるのです。この地上では「よそ者であり、滞在者」であることを自覚しつつ、天の故郷を望み見る者こそが信仰者です。先に召された人々もそのような信仰の証人として私たちを導いているのです。死は終わりではなく、新しい命の始まりです。(2025年11月)
「心は神の前に正しいか」
使徒言行録 8章14節~25節
フィリポのサマリア伝道によって多くの人々が洗礼を受け、新しい教会ができました。これを聞いたエルサレムの使徒たちは、ペトロとヨハネを派遣し、信じた人々の上に手を置いて祈ると、彼らは聖霊を受けました。サマリアの信仰者たちはイエスの名による洗礼を受けていましたが、まだ聖霊が降っていなかったのです。
この箇所は、水の洗礼と聖霊による洗礼を区別する根拠とする人もいますが、私たちは使徒言行録2章の「洗礼を受け、罪を赦していただくと聖霊の賜物を受ける」という文脈から、聖書全体のメッセージとのつながりを理解していきたいと思います。サマリアという地域性を考えると、ユダヤ人に軽蔑されていた民に福音が伝えられ、ペトロとヨハネがその信仰を確認した出来事は、ユダヤ人とサマリア人の垣根を越える重大な意味を持ちました。聖霊はエルサレムの教会とサマリアの教会を一つにし、福音が異邦人にも広がっていく第一歩となったのです。一方で、魔術師シモンのように聖霊の力を自分のものとしようとする者もいました。彼はお金を出して「その力を授けてください」と願い、ここから「シモニア」(つまり、教会における職務、地位をお金で買い取ろうとすること)という言葉が生まれました。神様の賜物を金で買おうとする考えに対し、ペトロは「お前の心が神の前に正しくない」と叱責します。聖霊は売買できるものではなく、神様の無償の恵みとして信仰によって受けるものです。
私たちもまた、神様を自分の願いを叶えてもらうための存在として利用していないか、奉仕や献金も周囲からの賞賛が欲しいといった思いが優先されていないか、聖霊の力を自分の私利私欲を満たす手段と考えていないかを振り返る必要があります。私たちが神様の御心を求め、御言葉に従う時に、聖霊は私たちを新しくしてくださり、私たちを「御心のままに」と導かれるのです。
ペトロはシモンに「この悪事を悔い改め、主に祈れ」と勧め、「赦していただけるかもしれない」と語ります。厳しい叱責の中にも赦しの希望が示されています。私たちは神様からの一方的な恵みとして与えられる聖霊と、十字架の主イエスからいただく喜びに押し出されて、福音、グッドニュースを伝えていくのです。(2025年10月)
「ステファノの説教Ⅰ」
使徒言行録7章1節~16節
ステファノは、恵みと力に満ちて不思議な業としるしを行い、主イエスこそ神が遣わされた救い主であると証ししました。その力強い伝道に対して、ユダヤ人たちは「モーセと神を冒涜している」と訴え、彼を最高法院に引き出しました。そこで偽証者を立て「律法と神殿を冒瀆している」と非難し、ステファノを裁こうとしました。
ここで問われていたのは、律法や神殿に依り頼むのではなく、イエス・キリストの救いによって真の神の民となる、という信仰の本質でした。ステファノは弁明においてイスラエルの歴史を振り返り、まずアブラハムを取り上げました。アブラハムは神の言葉を信じ、土地も子も持たぬ中で神の約束に従って歩みました。当時は律法も神殿もなく、ただ神の約束への信仰が彼を支えていました。ステファノはこれを示し、真の神の民とは目に見える制度に依存するのではなく、神の約束を信じる者であると訴えました。
続いてヨセフの物語が語られます。ヨセフは兄弟に妬まれエジプトに売られましたが、神は彼を用いて国を治めさせ、飢饉からイスラエルを救う備えとされました。ここにも、悲惨な現実の中で神の約束が実現する姿が示されています。信仰とは、神の導きに身を委ねることだとステファノは強調しました。
さらに「割礼」という契約が示されます。アブラハムに与えられた割礼は神の民であるしるしでしたが、後には誇りの象徴となってしまいました。新約の私たちに与えられたしるしは「洗礼」です。「洗礼」を通して、主イエスの十字架と復活による恵みを受け取ったことを告白します。しかし、洗礼も形式にとどまれば意味を失い、見える活動だけに依存するなら心が疲弊します。必要なのは御言葉に生かされる学びと祈りの生活であり、聖霊に導かれて、救いはただ主イエスの十字架と復活によって与えられるものだからです。
こうしてステファノは、目に見える律法や神殿に固執する人々に対し、アブラハムやヨセフの信仰を通して、目に見えない神の約束を信じて生きることの大切さを示しました。現代の私たちもまた、建物や活動といった形に依存するのではなく、主イエスによる救いの約束を信じて歩むことが求められています。(2025年9月)
「堂々と御言葉を語る」
使徒言行録4章 23~31節
7月に入ってからの子ども礼拝では、ピリポによるエチオピアの宦官の受洗、ペトロによる異邦人コルネリウスへの伝道、サウロ(パウロ)とバルナバの伝道旅行など、「伝道」が繰り返し語られてきました。これは教会の使命が、福音をのべ伝え、新たな人々を教会に迎えることであることを示しています。私たちは泉教会で「使徒言行録」を読み進めていますが、その中で強調されるのは、伝道が聖霊による教会全体で担うべき働きであるという点です。ペトロとヨハネが神殿で足の不自由な男を癒し、その奇跡を通じてイエスこそが救い主であると伝道した時、多くの人々が信じました。しかし、その伝道はユダヤの指導者たちからの迫害に直面します。それでも二人は「復活されたイエスの名による癒しである」と堂々と証ししました。これは、困難があっても福音を語る使命の重要性を示すと同時に、日本のような八百万の神々がいる伝道が難しい文化に生きる私たちにも重なる現実です。初代教会は、ペトロとヨハネのような使徒だけでなく、教会全体で困難に向き合いました。彼らが逮捕された際、教会の仲間たちは祈りによって支え合い、ペトロとヨハネも自らの経験を教会に報告しました。伝道は個人の業ではなく、祈りを通じて教会全体が担うものだという姿勢がここに表れています。
私たちの家族や身近な人への伝道も同様です。多くの信仰の仲間たちの祈りによって実現します。祈りによって伝道の業を共有することができます。ペトロとヨハネが仲間のもとへ戻って報告し、教会が心を一つにして神に祈った場面(4章24節以降)は、教会が信仰を共に告白する重要さを示します。彼らの祈りは天地創造の神を賛美し、旧約聖書の詩編を引用しつつ、現実の迫害も神のご計画の中にあると告白するものでした。そして彼らは「堂々と御言葉を語れるように」と祈り求めました。私たちも2000年前の初代教会と同じように祈り、信仰を告白し続けることができます。聖餐式においても、主イエスとの交わりを新たにし、信仰告白の言葉でもって心を一つにして語るのです。伝道は牧師だけの役割ではなく、私たち一人一人が神様に召され、用いられる働きです。「私は何もできません」と思う時も、神様は私たちを必要としておられます。その召しに応え、僕として従うことが求められているのです。
最後に、祈りが終わると教会が聖霊に満たされ、堂々と御言葉を語り出した(4章31節)ように、困難な状況の中でも聖霊が私たちを支え、祈りを通じて具体的な言葉と力を与えてくださることを信じ、歩んでいきましょう。自分を主人公とする生き方では体験できない恵みが、主イエスの僕となった者に与えられるのです。(2025年8月)
「美しの門で」
使徒言行録3章1~10節
本日の聖書箇所は、ペトロとヨハネが神殿に上る途中、生まれつき足の不自由な男に出会う場面です。彼は「美しい門」と呼ばれた門のそばで施しを求めており、人々の善意に頼って生きていました。彼が施しを求めたとき、ペトロは「銀や金はないが、持っているものをあげよう」と言い、「ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい」と彼を立たせました。すると男は躍り上がって歩き出し、神を賛美しながら神殿に入っていきました。
ペトロたちが足の不自由な男を「じっと見つめる」ところから物語は始まります。弟子たちは聖霊を受けて変えられ、相手を深く見つめ、関係を築くところから始めていました。私自身の伝道を振り返ると、私は相手を選びがちで、本当に御言葉を求めているかを見ようとせず勝手に判断しがちでした。しかし神様は、人間の思いを超えて働かれます。たとえば、私の義理の父は、まったく求道者に見えなかったにもかかわらず、晩年に洗礼を受けたことは、神の不思議な働きを示すものでした。
伝道とは、立派な偉人を見せることではなく、罪赦された「あるがままの私たち」を見てもらうことです。キリスト者も不完全で弱く頼りない存在かもしれませんが、主イエスによって赦され、生かされている姿を通してこそ、証しがなされます。現代でも教会には様々な動機で人が訪れます。金銭や癒しを求めて来る人もいますし、話を聞いて欲しいだけの人もいます。「ナザレの人イエス・キリストの名」にのみ信頼して人々に恵みを語るのが教会、私達のできることといってよいでしょう。
ペトロが男の右手を取って立ち上がらせたように、ただ言葉を伝えるだけでなく、共に歩む姿勢が求められます。当時、体の不自由さは悪霊によるものとされていましたが、キリストの名による癒しは、罪と死からの解放を意味する「しるし」でもありました。この男は立ち上がっただけでなく、神を賛美し、神殿の境内に入り、礼拝者としての歩みを始めました。人々は、その変化に驚き、「卒倒しそうになった」とさえ記されています。彼の姿は、主イエスが真の救い主であることの証しでした。2000年を経た今も、私たちは礼拝で神を賛美し、イエスがメシアであることを証ししています。教会は、「ナザレの人イエス・キリストの名」によって、罪と死の中から人を立ち上がらせ、神に向かって生かす場所なのです。私たちはこの恵みに感謝しつつ、御言葉を携えて歩みましょう。(2025年7月)
「信者の生活」
使徒言行録2章37~47節
本日の聖書箇所には、ペトロの説教を聞いた人々が「こころを打たれ」て「私たちはどうしたらよいのですか」と問いかける場面が描かれています。彼らは、神が送ってくださったメシアである主イエスを十字架につけてしまったという罪に愕然とし、その事実に心を深く揺さぶられました。この悔い改めは人間の努力によるものではなく、聖霊によってもたらされる神の恵みです。ペトロは主イエスの名による洗礼を受け、罪の赦しをいただくよう勧めます。洗礼を受けた者には「賜物としての聖霊」が与えられ、教会の一員として導かれます。三千人がこの招きに応じ、教会が誕生しました。教会に連なる信者の歩みには四つの特徴があります。
一つは「使徒たちの教えを守ること」、すなわち神の御言葉を第一に聞くこと。二つ目は「交わりをなすこと」。み言葉に心を動かされた者は自然と信仰の仲間との交わりへと導かれます。そしてその交わりの中心が「パンを裂くこと(聖餐)」と「祈ること」です。聖餐とは、主イエスの十字架での死を記念し、その救いを共に分かち合うことであり、教会員は「陪餐会員」として、共に恵みを味わう存在です。また、祈りを分かち合うことも、交わりの基本であり、神の前に一つとされるために欠かせません。
さらに、教会では互いに物を分かち合う具体的な助け合いもありました。自分の財産を進んで捧げ、必要に応じて配分することで、信者同士が「一つとされて」共に生きる共同体が形づくられました。この支援は仲間意識や人間的な好みによるものではなく、主イエスの恵みを共に受けた者としての応答でした。こうした生活は周囲の人々にも影響を与え、民衆全体から好意を寄せられました。
私たちも困難の中にあって、聖霊の促しに従い、悔い改め、祈り合い、交わりの中に戻っていくとき、神様の愛とご計画を味わう喜びが与えられます。主イエスが新しい仲間を私たちに加えて下さいます。主イエスへの信仰を告白し、聖餐を共にし、共に祈る仲間を迎え入れ、互いに主の恵みに感謝しつつ歩んでいきましょう。(2025年6月)